
|
霧 「ねえ、貴女は今のあたしの気持ちって分かる?」 「はあ?」 あたしの言葉に、彼は訝しげな顔をした。 霧が漂う森には、あたしと彼の姿しか見えない。 「はあ? じゃないでしょ。ちゃんと答えて」 「な、何だよ急に…………」 あたしが、ずいっと身を寄せて迫ると、焦ったように一足下がった。 ふふっ、やっぱりこうでなくちゃね。 「姐さん、また冗談ですか……」 「あら、何で?」 「口元、笑ってる」 嫌だ。ついつい、顔に出てたみたい。 あたしは、緩んだ口元をぎゅっと結んだ。 「ふーんだ。つまんなーいの」 そして、わざと大げさにそっぽ向いてみせる。 いつもだと、こんな風にあたしが接すると必ず「はいはい……」って諦めてくれるのよね。 自分の行動に対する反応が楽しくて、会うたびにからかってるってことを知ったら、怒るかしら? そんなことを考えながら待っていたのに、いつもはすぐ返ってくる反応がなかなかこない。 いくらなんでも、これ以上そっぽ向き続けるわけにはいかない。 そう思って、横目でちらりと覗き見ると、彼は木に寄りかかって、眠そうに欠伸なんてしている。 すぐ近くにある葉から、露がこぼれ落ちていくのが見えた。 その様子に、何だか拍子抜けしたというか、こっちとしてはあまりにも予想外の反応に思わず眉をしかめた。 「…………」 無言の圧力に気付いたのか、彼の視線があたしへと向かう。 「あ、分かった」 「何が?」 あたしの怒った顔を見て、彼が楽しそうに笑う。 「ラナの今の気持ち」 言われて、もう怒るどころか半分呆れてきた。 あたしの今の気持ちが分かったって今更言われても、そんなのもう答えが出ているようなものじゃない。 「ふーん……。じゃあ、当ててみて」 わざと口元に笑みを作り、目だけは挑戦的に相手に向ける。 彼は、あたしの視線を外すこともなく、真っ直ぐに見返してくる。 彼の唇が微かに動いた。 「悲しい」 全く予想もしなかった答え。 「……あら、それは何故?」 今、自分はどんな顔をしているのだろう。 自分では必死に笑ってるつもりだけど、この人の目にはそれも嘘に見えるのかしら? しだれかかった髪を耳にかけた。 「うーん……。ラナが怒ってたから?」 「それって、悲しいって答えと繋がらないでしょ」 そういって彼を急かすと、何だか困った顔で笑うから、いよいよ理由を聞いてみたくなった。 纏わる霧を鬱陶しそうに払う彼に、ゆっくりと近づく。 一歩一歩進むたびに、お互いの視線が混じり合うのが、鮮明に分かった。 お互いの距離が大分縮まった時、あたしの考えが分かったのか、彼は慌ててその場から離れる。 でも残念。もう遅かったわね。 あたしは、彼の腕を掴みそのまま自分の体重を乗せて、押し倒した。 どさっと音がして、彼の苦痛に歪む顔がよく見えた。 「ほら、早く言いなさい。早く言わないと……」 自分の顔をすっと彼の首筋に近づけた。 あたしの髪が、彼の胸元にぱらぱらと落ちていく。 「…………食べちゃうわよ?」 舌で上唇を舐める。 彼の喉元がゆっくりと動いた。 「分かった!! 分かった!! 言いますよ!!」 「分かればよろしい♪」 いつもの調子に、あたしは彼の上から降りる。 顔を真っ赤にさせた彼は、地面に座りながら不本意そうに襟元を直す。 そして、一呼吸おいてあたしに言った。 「怒りの正体は悲しみなんだってさ」 その意味を問いたださないあたしに、彼は続ける。 「ラナ、さっき俺が無視したこと怒っただろ? それって、ただ怒ったんじゃなくて、俺が無視したことが悲しかったから怒ったんじゃないか?」 「自分のことを分かってくれないから、分かって欲しかったから悲しかった……」 「だから、悲しかったんじゃないかって思ったんだよ」 彼の視線があたしを捕らえる。 その瞳に、あたしの姿がどう映っているかなんて、あたしには見えはしない。 「ま、これって本に書いてあったことの受け売りなんだけどな……」 少し、ばつが悪そうに笑う彼の姿にハッとする。 「そう……」 答えた返事が、あまり気乗りしない風に聞こえたのか、機嫌を窺うように彼はあたしの顔を覗き込む。 「何?」 「ん? いや……当たってたのかな〜ってさ」 彼の言葉にふっと笑うと、自分の人差し指を彼の唇に押し当てた。 「それはー……ひ・み・つ♪」 「おいっ!」 おどけた口調でいうと、怒った彼があたしを掴まえようと手を伸ばした。 あたしは、ふふっと笑うと、すっと後ろに下がる。 彼の手が、漂う霧を掴んだ。 「あら、残念。あたしは、そう簡単には捕まらないわよ?」 そういって、また一歩ずつ後ろに下がった。 この霧の中では、少しでも距離をあければその分だけ相手の姿が見えなくなってしまう。 今、彼の目にあたしの姿は霞んでいるのかもしれない。 あたしの目に映る彼が、朧気に霞んでいるのと同じように。 二人の間に流れる霧は、決して晴れることはない。 それは、この夢の世界が何も変わらないのと同じこと。 いつ終わるかも分からない、霧の様な夢の中。 いつか貴方の姿が、あたしを置いて消えていく気がした。 END 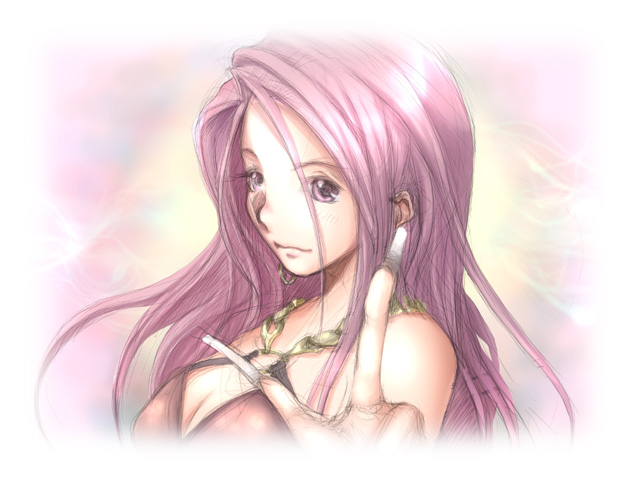
「霧」 小説執筆:藤元 // 挿絵:倉持 諭
(C)2006 TAKUYO co.,ltd. |
